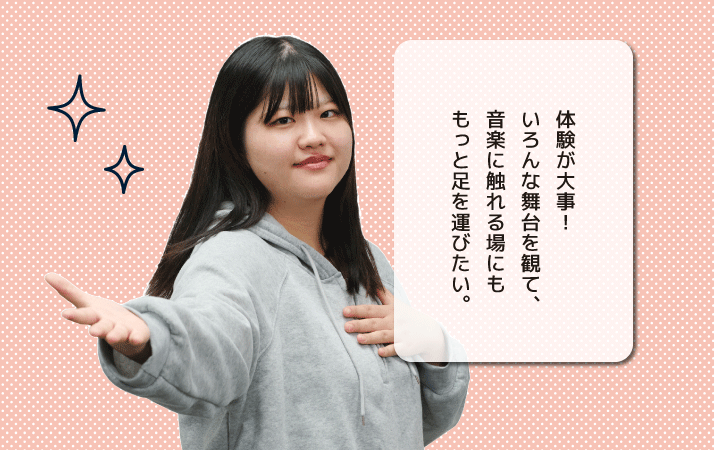メディアコミュニケーション学部
こどもコミュニケーション学科

旭彩希先生による「乳児保育Ⅱ」。3歳未満児の発育・発達に応じた援助や関わり方について、知識と実践の両面から学ぶ。
大学の先生は、それぞれの専門分野やテーマを持つ研究者でもあります。「専門ゼミナール」(3年次)はその研究の一端に触れ、さらに自分自身の研究に向けて、学びの専門性を高める科目です。扱われるテーマの幅広さと奥深さは、大学ならではの学びの魅力を改めて感じさせてくれます。たとえば「実験・調査によって集めたデータをもとに、子どもの発達を心理学の視点から研究する」「子どもへの虐待、貧困といった問題に着目し、子どもの最善の利益と、それを保障する方法について考える」などのほか、子どもと音楽、子どもと博物館、児童文学、子どもへのスポーツ指導についてなど、複数の視点、学問領域に関わるものもあります。自分の興味や志向に合わせてゼミを選択し、それぞれのテーマに基づく専門的な知識を深め、研究の手法を学びます。また、実践を通して知識を深め技術を身につける科目も充実しています。たとえば「乳児保育Ⅰ・Ⅱ」(3年次)では、乳児保育に携わる保育者の役割や、発育・発達の過程と特性をふまえた援助・関わり方について学び、現場で必要とされる知識と技術を実践によって身につけます。そして実践の中で気づいたことや、学修を通して興味を持った分野と子どもとの関わり、専門ゼミでの学びと自らの視点とを結び合わせて発見したテーマが、4年次の卒業研究へとつながっていきます。
Student Interview
LGBTQ の人たちと話す中で「その人のあり方を、個として受け入れてもらいたい」という言葉に触れ、とても印象に残りました。子どもとの関わり方についても、同じような課題があると思います。一人ひとりの個性や特性、発達に対してどう関わるのが望ましいのかを考えていく上で、ひとつの視点が得られたように感じました。今後は児童福祉司など、子どもたちを内面からも支えられるような仕事に就くことを目指して学び、自分の強みとなるものを見つけていきたいです。
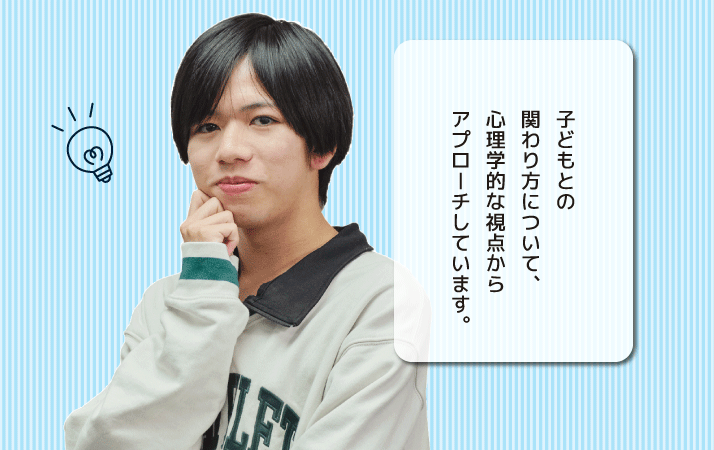
専門ゼミの魅力は、自分の興味を軸に学びを深めながら、ゼミ生それぞれの視点にも触れられることです。もともと音楽が好きだったことに加え、「器楽表現の技術」や「幼児と表現」での学修から、音楽と子どもの関わりについて特に興味を持つようになりました。ゼミでは取り組みの一環として、ミュージカルを鑑賞する機会も。劇中の歌や音楽、振り付けはもちろん、ステージのセットや照明の効果にも着目し、総合的な表現の魅力を体験しながら学ぶことができました。