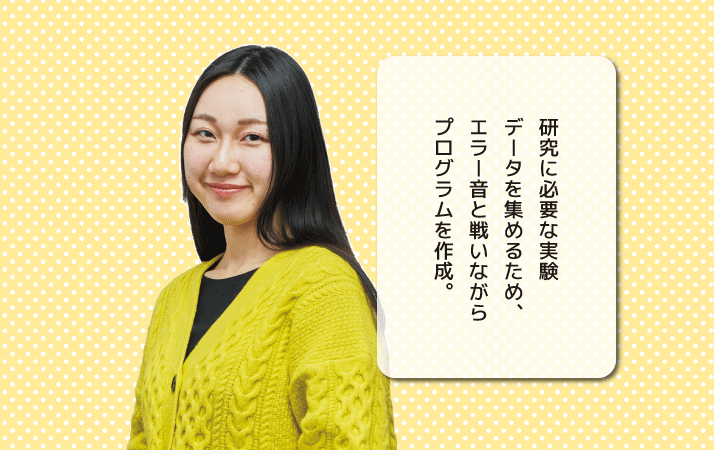社会学部
人間心理学科

浅岡章一先生、野添健太先生らの指導を受けながら睡眠実験を実施。心理学の幅広い分野に関連するところも「睡眠」の魅力。
人間心理学科には睡眠心理学を専門とする教員が複数在籍しており、睡眠と心の関係や、睡眠にまつわる諸問題について扱う睡眠心理学分野の本格的な学修・研究に取り組むことが可能です。また「睡眠の生理心理学」をはじめ、授業の中で睡眠と心の関係について扱う科目が複数設置されている点も、本学科におけるカリキュラム上の大きな特長となっています。
各教員の研究室では、不眠の認知行動療法に関わる研究や、睡眠公衆衛生学的研究、睡眠実験心理学的研究など、睡眠心理学分野のさまざまなテーマでの研究が進められています。これらの研究を行うための実験用防音室や脳波計といった設備も充実しており、授業の一環として行う実験・実習や、4年次に取り組む卒業研究でも積極的に使用されています。
科目例①
睡眠の生理心理学睡眠の基本的なメカニズムや、心の問題と睡眠との関連について幅広く学びます。授業では睡眠の生理学的現象をはじめ、睡眠中の心理学的現象、睡眠障がいについて理解を深めるほか、睡眠の評価法や改善技術などについても学び、睡眠改善策の提案と助言のための基礎知識を身につけていきます。「大学認定睡眠改善インストラクター」試験を受験する場合は必修となる科目です。
科目例②
睡眠と認知の心理学眠気が「認知機能」に与える影響について学びます。注意や記憶、心霊現象を信じる認知的メカニズムといった幅広い認知機能を扱い、睡眠との関連を考察します。
また、学生が考えた睡眠研究のアイデア発表も行います。複数の睡眠研究者によるパネルディスカッションが行われることもこの授業の特徴のひとつ。睡眠に関わるさまざまなテーマについて、本格的な議論が展開されます。
研究例①
乱れた睡眠と心の関係を探る作業スピードや正確性、記憶、推論、エラーへの気づき、そしてストレス耐性などに与える睡眠の影響を検討するために、徹夜中の認知機能の実験的測定や、睡眠慣と作業成績との関連についての調査を行っています。さらに表情認知や共感性、共同作業パフォーマンスなど「社会的認知機能」にも着目することで、不眠や夜更かしが心や生活に与えている影響を明らかにしようとしています。
研究例②
睡眠中の夢を科学するヒトは一晩に複数回の夢を見ていると考えられています。夢を見ている可能性が高いレム睡眠にある実験参加者を覚醒させ、直前まで見ていた夢について尋ねる手法を用いた研究が行われています。このほか、睡眠中に刺激を与えることで「夢見報告」がどのように変化するかについての研究や、記憶に残りやすい夢の特徴の研究、夢の中の色彩や時間感覚に関する研究なども行われてきました。
Student Voice
睡眠統制実験の参加者となった際は、ふだんとは違う自分のネガティブな思考に戸惑い、睡眠の乱れが心に与える影響を体感することができました。卒業研究でテーマとしたのは「夜間断眠時におけるポジティブ感情の喚起は認知機能を維持向上させるか」という問い。社会的・学術的意義を持った研究を目指して、試行錯誤を繰り返しました。