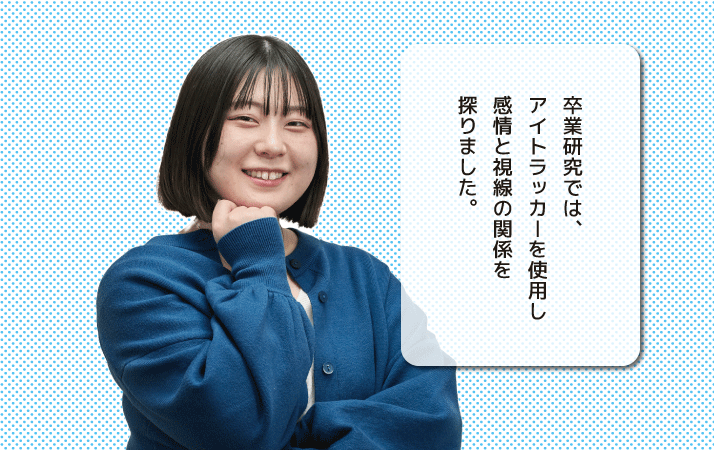社会学部
人間心理学科

石橋美香子先生が専門とする発達心理学では、乳幼児(1~2 歳頃)と保護者の協力を得ながら調査を行うことが欠かせない。
発達心理学では、私たちの認識や行動が、時間とともにどのように変化するのかを、一般的な法則性に基づいて説明し、また、私たちの認識や行動が変化する要因を探ります。関連科目では、ヒトの心身の働きや機能が、文化や社会による影響を受けながら生涯にわたってどのように発達していくのかを学びます。たとえば「発達心理学Ⅰ・II」では、胎児期から老年期に至る、ヒトの発達に関する基本的な理論や概念について広く学びます。また、心の変化のしくみや体系を知る上で必須となる「子どもと家族の臨床心理学」では子どもの発達の多面的な理解や支援方法を、「青年心理学」では青年期にみられる課題や対人関係などを学ぶことができます。また3年次には「発達心理学演習」で観察法や発達検査など発達心理学の研究方法を専門的に学びます。
科目例①
発達心理学演習観察と検査・測定による、発達心理学の研究方法を学びます。観察法についてはその基本を学んだ上で、実際に心理学研究などに用いられるソフト「ELAN」を使用し、観察映像による分析・研究方法を学びます。さらに、研究・臨床で使用されるアセスメントツール「ESCS」を用いた検査など、幼児の発達を調べる方法や、幼児の養育者に対して行われる質問紙調査などについても学びます。
科目例②
青年心理学生涯発達の一過程としての青年期には、特有と考えられている課題や現象が数多くあります。たとえば親からの自立のような親子関係の変化、対人関係の親密化がもたらす親友や恋人の獲得、アイデンティティの形成などが挙げられます。本科目では現代における青年の「自己機能」と「対人関係機能」に関連した最新トピックの検討を通し、「青年期」や「青年」についての心理学的理解を深めます。
研究例①
乳幼児期の子どもの空間認知の発達に関する研究1~2 歳児の「視線行動」(目の動き)とおもちゃの扱い方の行動観察を通して、空間認知の発達とその関わり方を調べる研究です。たとえばおもちゃが動いたり、隠れたりといった場所の変化への理解を示すような「注視行動」(見つめる、探す
など)と、おもちゃへの関わり方を観察することで、子どもがどのようにモノの機能や特性を理解し、それに応じたふるまいができるようになっていくのかを調べます。
研究例②
障がいに対する個人の考え方を探る社会の中で関心が高まっている事柄への理解を深めるための研究も行われています。たとえば障がい児・者について、見聞きすること、実際に関わる場面は日常的にも多くありますが、障がいに対するイメージや捉え方は、どのように形成されるのでしょうか。障がいに関する知識や経験が豊富であるほど障がい児・者との社会的な距離が近くなり、肯定的なイメージを持ちやすいことが明らかになっています。
Student Voice
発達心理学の分野に注目したのは「学習・言語心理学」などの科目がきっかけ。特に喃語(なんご)など、乳幼児期の言語発達について興味を持ちました。専門ゼミでは文献の内容をもとに、言葉の発達と身体(運動)の発達の段階・時期を比較するなど要約資料を作成。新しい気づきと学びを得る機会になりました。