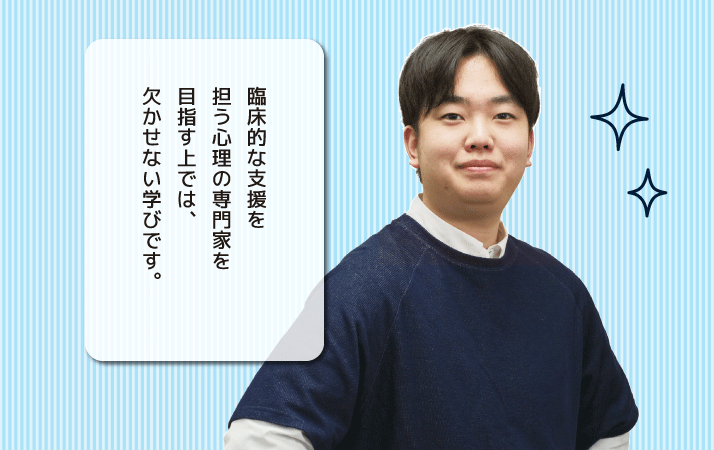社会学部
人間心理学科
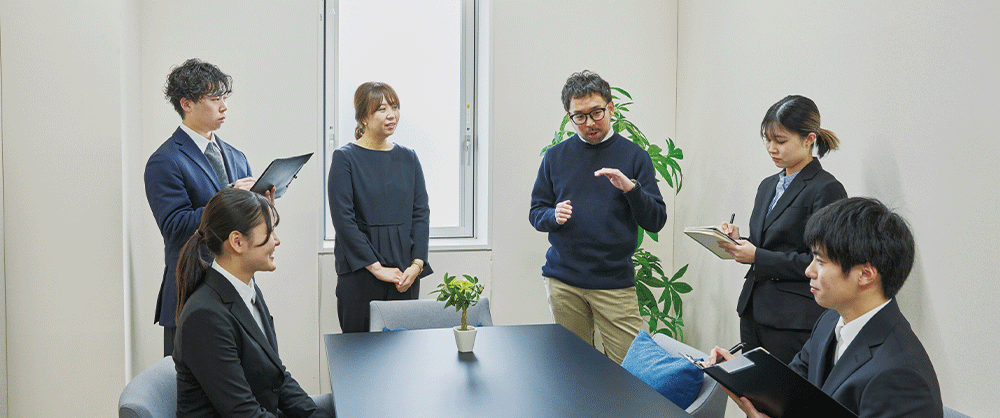
山本隆一郎先生・尾花真梨子先生の指導を受けながら、心理相談センターで心理実習を模した演習に取り組む。公認心理師を目指す上で重要なステップとなる。
臨床心理学の実践の場は、医療・保健、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働と幅広い領域にわたります。心理に支援を必要とする方(要支援者)の「困りごと」もまた多様であることから、臨床心理学はさらに複数の分野に分けられています。たとえば一人ひとりの苦悩や不適応を理解する(心理的アセスメント)ための分野や、心理的支援法について研究する分野、各領域での実践を行うために必要な内容を研究する分野もあります。本学科のカリキュラムには、これらの各分野について学ぶ科目に加え、3年次には臨床心理学に基づく知識や技術を実践的に学ぶ「心理演習」、4年次には実際に心理的支援が行われている機関や施設で実習を行う「心理実習」が設置されています※。また必要な科目を学ぶことで、心理職の国家資格「公認心理師」を目指すことも可能です。
科目例①
健康・医療心理学ストレスと心身の疾病との関連、うつ病や不安症、生活習慣病や慢性疾患など、主に保健・医療の分野で扱われる「心理社会的課題」について理解を深めます。病院などの医療現場、あるいは保健所や学校など保健活動が行われている現場において扱われる課題と、その支援について扱います。また大規模地震など、災害が発生した際に必要となる心理的支援についても学びます。
科目例②
心理演習/心理実習「心理演習」(3年次)では、要支援者の心理状態の観察、その結果の分析および要支援者や関係者に対する援助方法を学びます。また多職種連携や地域援助、チームアプローチについても体験的に学びます。「心理実習」(4年次)では、「心理演習」での学びをふまえ、医療・保健、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野における心理に関する支援について、学外での実習を通して学びます。
研究例①
苦悩・不適応に関連する要因を探る抑うつや不安、不眠、ストレスといった問題を理解し、支援策を検討するために、これらに関連する「変数」(問題の原因や、状態を変化させる要因になるもの)を探索・検討する研究が行われています。たとえば、オンラインで実施できる認知課
題、アンケートなどを用いて、パーソナリティや家庭環境、友人関係、認知情報処理の特徴といった変数と苦悩・不適応との関連性を検討する研究などがあります。
研究例②
心理学的支援法の効果を検討する苦悩や不適応を改善するための心理的支援法を開発する研究に加え、その心理的支援法の有効性や有用性を検討する研究が行われています。こうした研究の手法として、すでに効果が実証されている支援法と新しい支援法を実施して効果比較をする「介入研究」のほか、介入研究の成果を報告した複数論文からその効果に関するデータを抽出し、統計学的に統合する「メタ分析研究」などがあります。
Student Voice
「心理実習」の中でも、特に医療や福祉分野での実習に取り組んだことで、改めて臨床心理学分野への興味を強くしました。実習中には不安や緊張感を伴う場面も多かった一方で、心理的な支援の実際的な取り組みに触れ、関連する知識を実体験も交えながら身につけられたという充実感がありました。