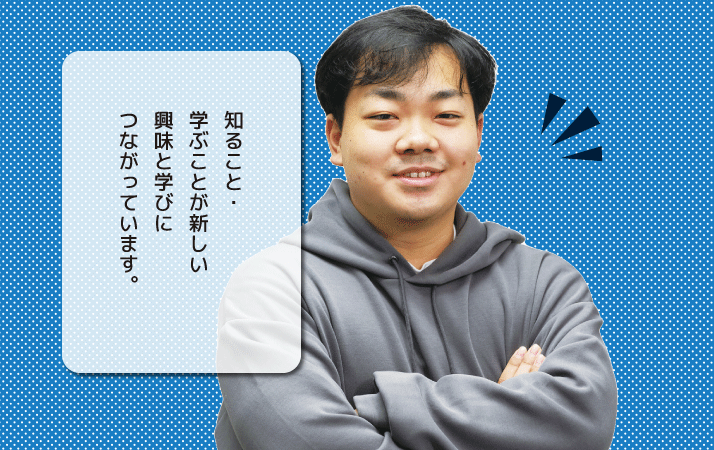社会学部
現代社会学科

環境学ゼミ(自然共生社会)では、中部山岳国立公園の一部をなす上高地を視察。穂高連峰などを望む山岳景勝地として知られ、人気の観光地でもある。
国立公園、鳥獣保護区、世界自然遺産、ラムサール条約登録湿地、世界ジオパーク、ナショナルトラスト、サンクチュアリ……これらは「保護地域」と呼ばれ、自然環境や希少生物の保護などを目的に、さまざまなかたちで指定されたものです。
本ゼミナールではこうした保護地域が持つ価値や意味、あるいは観光化による問題などについて理解を深めます。フィールドワークでは主に野外活動を行い、エコツーリズムや代表的な保護地域である国立公園の管理運営について、体験的に学びます。
また大きな社会問題になりつつある外来生物による被害、シカやイノシシ、クマなど大型鳥獣の分布拡大と個体数の急増、絶滅危惧種の問題など、人間の営みによって変わりつつある動物と人間の関係性についても正しく理解し、解決の糸口を見つけるための学びに取り組みます。視野を地球規模へと広げ、自然保護と活用の方法を考えていきましょう。

中島 慶二 先生
「事件は現場で起きて」います。法律や制度や予算、すべては現場の問題を解決するためにあるといっても良いでしょう。現場で課題をとことん突き詰め、方針を打ち立て、関係者の説得に力を尽くすこと、そうして得られた現場の改善などの成果や経験は他に代えがたいものがあります。「現場に始まって現場に終わる。」です。
Student Interview
大自然に囲まれる上高地から身近な地域まで、さまざまな自然環境の中で生物に触れるフィールドワークは、インターネットや書籍の情報からは得られない、五感で感じる学びや体験の機会に。夏休みには、自然環境への負荷を抑えた「堆肥づくり」に挑戦しました。堆肥ができるしくみなどを事前に学んでいましたが、微生物によって材料が分解され発酵するときの熱を肌で感じることができたのは、実際に作業をしたからこそ得られた経験でした。