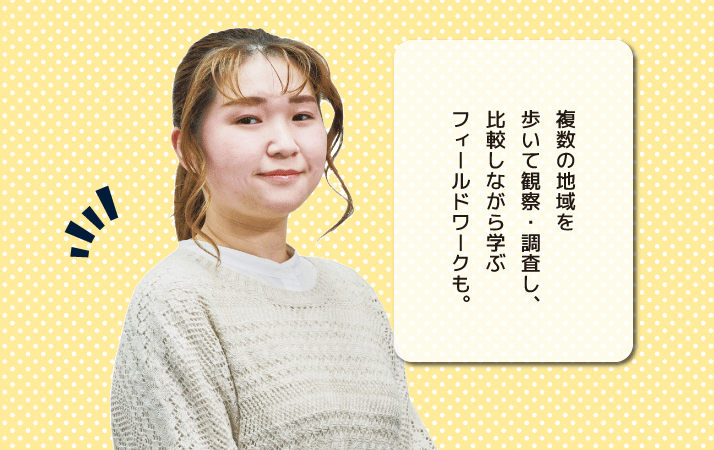社会学部
現代社会学科

阿南透先生によるガイドで、寒川神社(神奈川県)御神門の「迎春神話ねぶた」を視察。フィールドワークを通して神社仏閣や祭りの背景にあるストーリーが見えてくる。
民俗学は、地域の習慣や生活様式、祭礼、妖怪といった、人々の暮らしに受け継がれてきた文化の研究を得意としています。これらは“古き良き伝統文化” などと紹介されがちですが、決して過去のものではありません。さまざまに変化しながら、現在の暮らしの中に生き続けているのです。
本ゼミナールでは、主に戦後~高度成長期~現代に至る生活の変化をたどり、私たちの生活や考え方の中にある“生きた伝統文化”を探究します。「コロナ禍の生活」「令和大礼」「アニメ聖地巡礼」「妖怪とまちおこし」「テーマパーク」「祭りとイベント」「就活祈願」など、自らが興味を持ったこと、発見したテーマを掘り下げていく学びが魅力。文献、マスメディアやネット、行政資料などから情報を集め、フィールドワークでたくさんの人に会って話を聞いたり、街や暮らしを観察したり。そうした「質的調査」から、日常の中にある文化とその変化について考えます。

阿南 透 先生
日常生活を学問にするためには、身の回りのことに対して「なぜ?」という疑問を持ち続けることが大事です。その疑問を深く追究していくための手段が民俗学です。
Student Interview
ふだん生活している中で「当たり前」になっていることを、改めて見直していくところに民俗学の魅力を感じています。現在はさまざまな「祭り」があり、地域住民
だけでなく観光客向けに開催されるものも少なくありません。一方「人々が神を迎え、もてなす行事」としての祭りには、その土地に暮らす人々の信仰や、神から恩恵の捉え方などが表れます。こうして視点を変えて異なる魅力を見つけ、昔と今を比較して謎を解いていくような学びにワクワクしています。