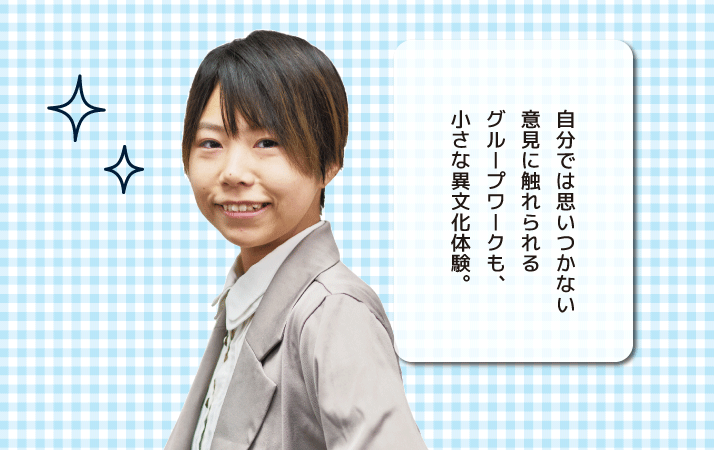社会学部
現代社会学科

文化人類学ゼミでは台湾を訪れ、人々の行動や文化の違い、食、歴史、観光などのテーマで調査。観光旅行とは違う発見と感動が味わえる。
雨上がりの空に広がる虹。あなたの目には、何色あるように見えますか?「もちろん7色でしょ」と即答したあなたは、自分が“文化の色メガネ”をかけていることに気づいていません。異なる文化圏では、虹は6 色とされたり、3 色だとされたりしています。日本でも、かつては7色とはいわれていませんでした。
文化人類学を学ぶ上で大切なもののひとつが、異文化を鏡としながら自らの常識や価値観、つまり「当たり前」や「普通」を見つめなおす姿勢です。本ゼミナールでは、アフリカやオセアニアなど世界のさまざまな地域で生きる人々の暮らし、あるいは私たちが暮らす街の中にも広がる“異文化”を取り上げ、人間の生の多様性と可能性について考えます。
こうした学びには、フィールド(調査研究対象となる場所や環境)での出会いと発見が欠かせません。身近な街でのフィールドワークでは、調査のコツや自らの経験と気づきを言語化するスキルを学びます。

川瀬 由高 先生
文化人類学の面白さは、自分のそれまでの常識や思い込みを揺さぶるような新たな価値観に気づかせてくれることです。他者との「違い」を価値の優劣で判断するのではなく、その「違い」を尊重し、そこから新たな視点を学ぶこと。これが、文化人類学が最も大切にする姿勢です。
Student Interview
文化人類学の文献講読を通してさまざまな文化に触れる中で、特に印象に残ったのはインドネシア・バリ島における「上下の秩序」や浄・不浄の感覚について。国際化が進む中、その土地の文化・習慣に強く根ざした価値観をどう扱うか、立場や状況によって異なる考えが導かれるのがおもしろく、深く考えさせられました。また音楽人類学やスポーツ人類学といった特定分野からのアプローチも、現代の問題を具体的に捉え、考えるヒントになりました。